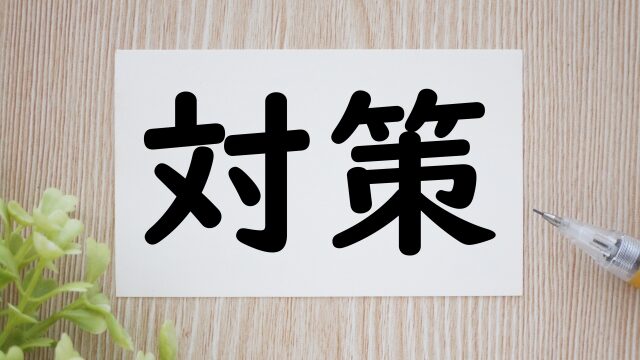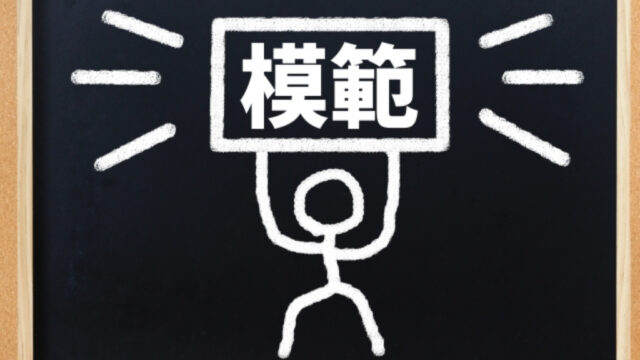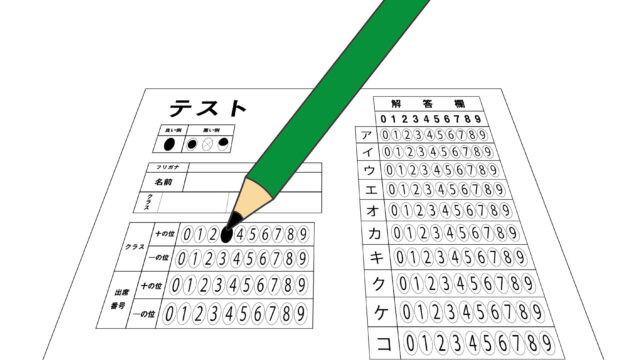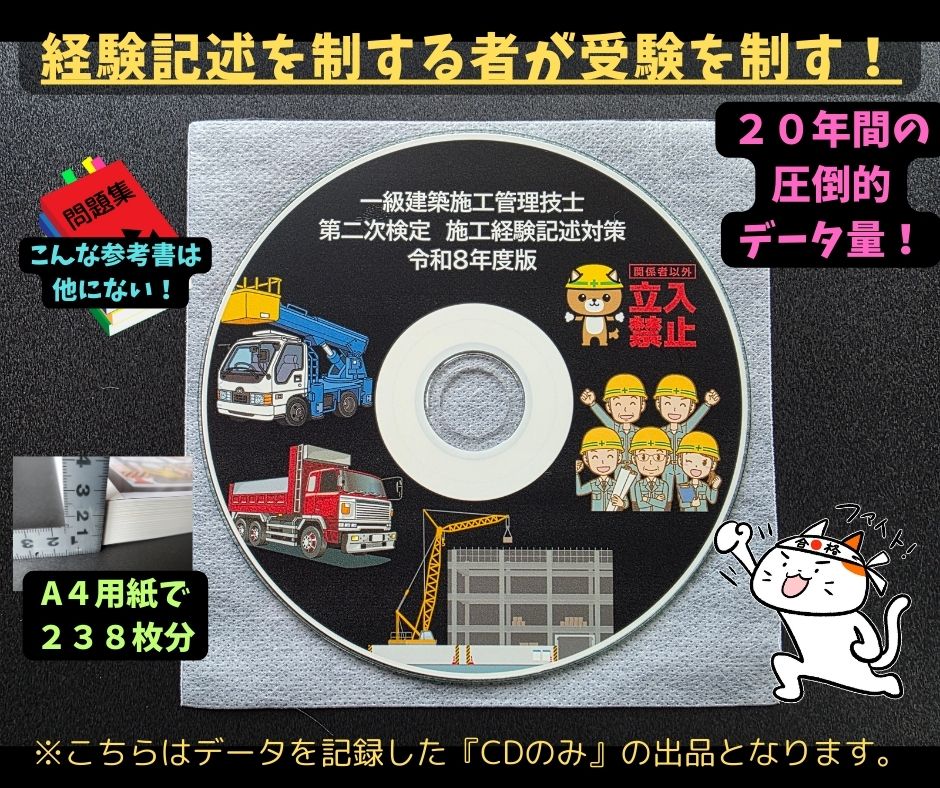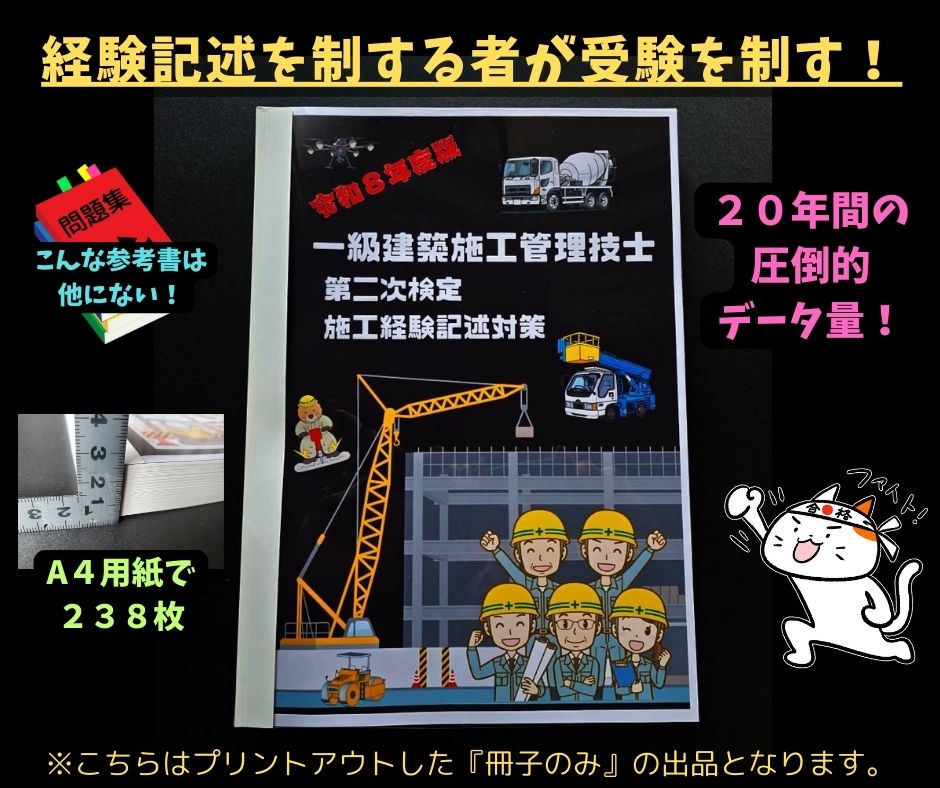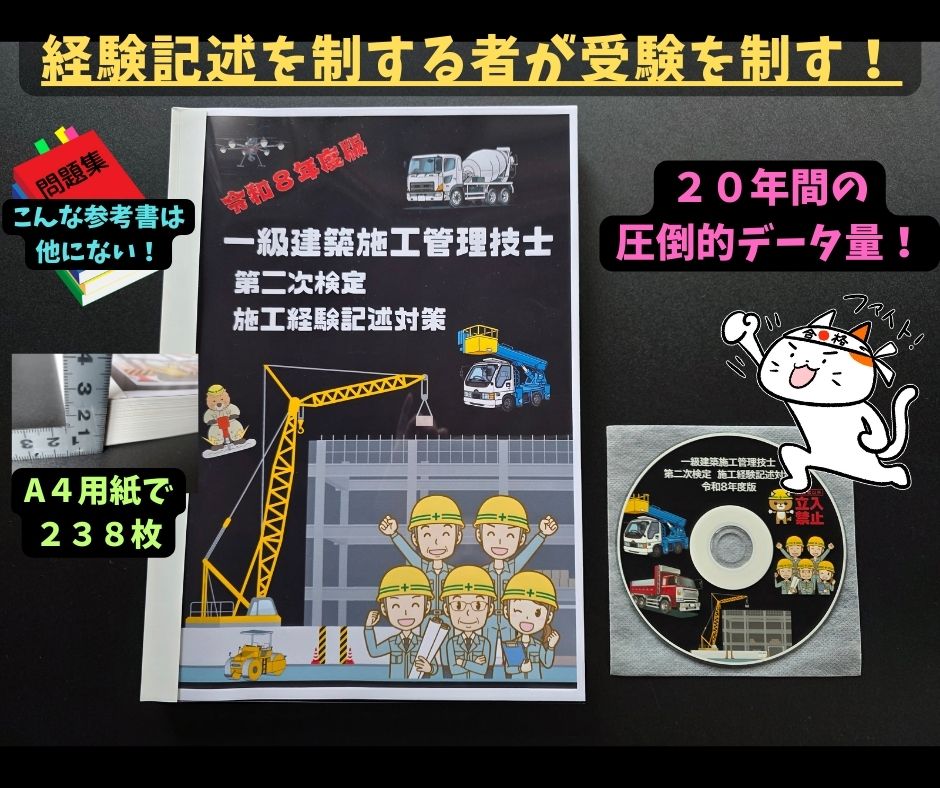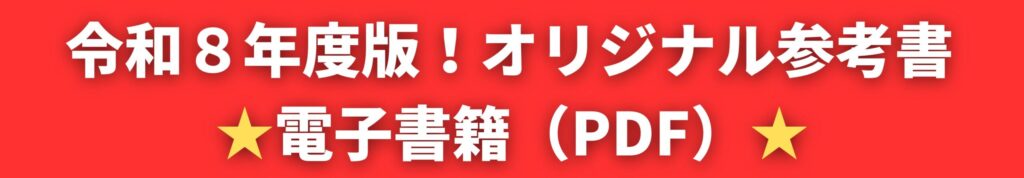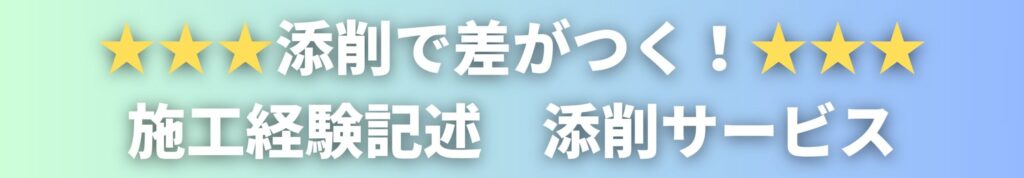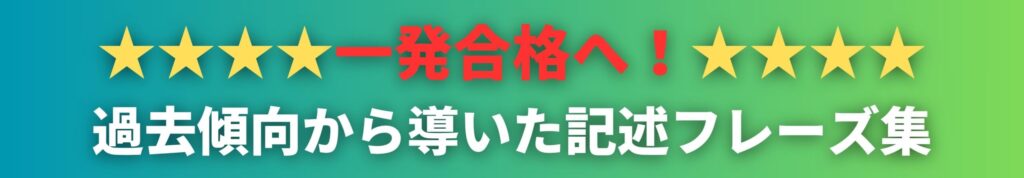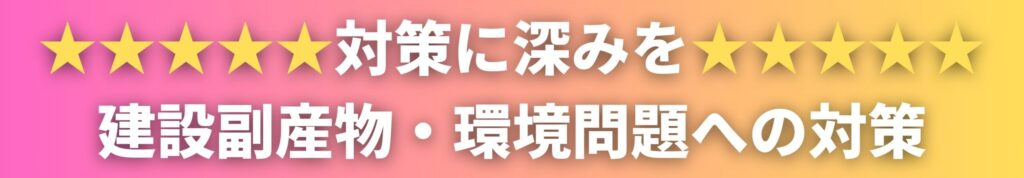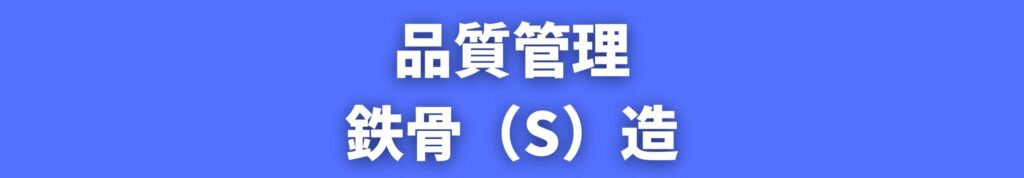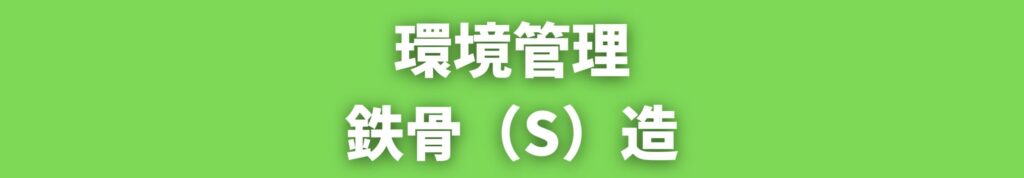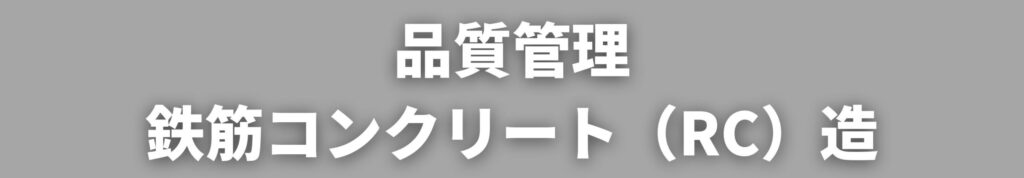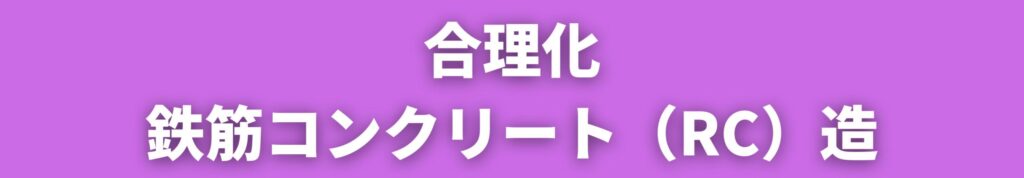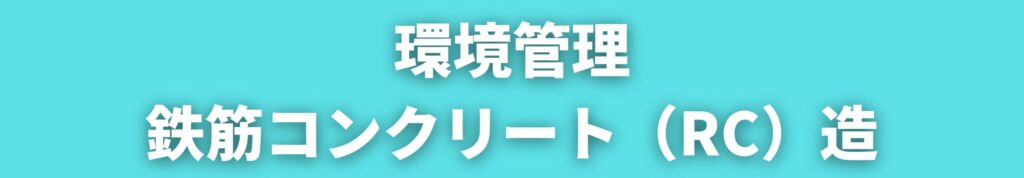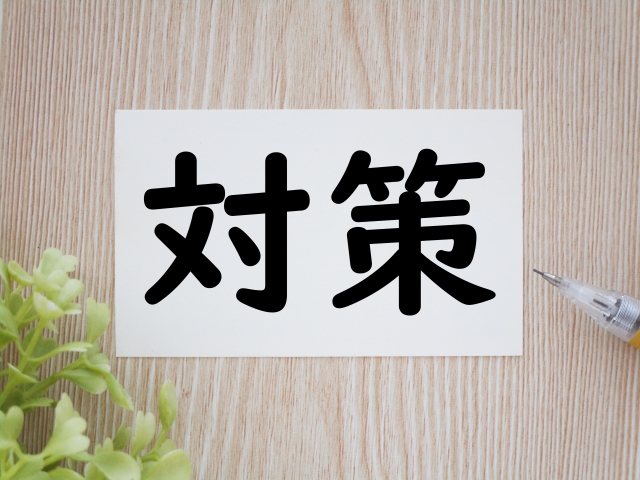施工経験記述の書き方は千差万別。
しかし、その中でも良い書き方、良くない書き方というのがあります。
ここでは良い書き方、良くない書き方というのを解説していきます。

良い書き方とは?良くない書き方とは?
施工経験記述の書き方と言われても実際に書いてみると中々難しいもの。
しかし、語句の使い方によっても表現は変わります。
こればかりは繰り返しの学習により身体で感じるしかないと思います。
問題1
施工計画を行う上で、留意した事項を上げ、
それぞれに対して、具体的な対策又は処置を3つ記述しなさい。
留意事項:敷地が狭く歩道もない為、仮設工事や掘削工事、資機材の搬入計画に留意した
具体的な対策又は処置
| ① | 良くない書き方 | 仮囲いの許可申請を提出し、出来るだけ広い幅を確保した。 |
| 良い書き方 | 仮囲いの為の道路占有許可を申請し、90cm幅の許可を受け枠組足場架設のスペースを確保した。 | |
| ② | 良くない書き方 | 資材の取込みは、路上にトラッククレーンを配置して出来るだけ短時間に荷揚げした。 |
| 良い書き方 | 資材の取込みは1階、2階の前面壁と2階床梁をあと施工とし、そこに資材車両を入れてタワークレーンで荷取りした。 | |
| ③ | 良くない書き方 | 奥から掘削し、手前の掘削は早朝に道路側から安全監視員を配置し掘削を行った。 |
| 良い書き方 | 掘削は桟橋を設置し、根切り底にブルで集土して油圧伸縮バケットで搬出した。 |
出来るだけ具体的な数字を書きましょう。
そして、一級建築施工管理技士らしい、内容が詳しい施工経験記述の書き方に努めましょう。
専門用語を多く用いると、それらしい文章になります。
とにかく書いて数をこなすのみ。
問題2
施工計画を行う上で、留意した事項を上げ、
それぞれに対して、具体的な対策又は処置を3つ記述しなさい。
留意事項:隣接にはRCの中層建築があり、
地下水の流出が確認された為、山留め施工計画に留意した。
具体的な対策又は処置
| ① | 良くない書き方 | 多少の地下水流出が予想されたが、親杭横矢板工法を採用した。 |
| 良い書き方 | 地下水の流出が予想されたので山留め壁はSMWを計画、一段鋼製井桁切梁工法を採用した。 | |
| ② | 良くない書き方 | 地下水の排水工法は、重力排水とする計画とした。 |
| 良い書き方 | 地下水の排水工法は、重力排水とし釜場を4箇所設け、水中ポンプ3インチによる揚水とした。 | |
| ③ | 良くない書き方 | 地下工事は、早朝の道路側からの作業として、仮囲いを作業中は取り外し終了後設置とした。 |
| 良い書き方 | 敷地に余裕がない為桟橋を設置し、桟橋は道路から1/6勾配で構築した。 |
1. 施工計画の目的と全体像を明確に
- 施工計画の目的を明確に記述します。例えば、工事の効率性を高める、そして品質を確保する、安全性を確保するなど、施工計画が達成しようとする目標を説明します。
- 計画が現場全体にどう影響するか、そしてその全体像を示すことで、計画の意図を明確に伝えます。
2. 工程表と工期の設定
- 工程表の作成と、それに基づく工期の設定について説明します。さらに具体的に、どのようにして各工程のスケジュールを組み立てたか、他の工種との調整やクリティカルパスの管理方法などを記述します。
- 工期の短縮や遅延を防ぐための対策についても触れると良いでしょう。
3. 資材・機材の手配と管理
- 必要な資材や機材の手配方法や、それらの管理方法について具体的に記述します。そしてどのようにして適切な時期に資材・機材を現場に届けるか、保管方法や品質の維持についても説明します。
- 資材や機材の調達におけるコスト管理や、リスクの回避策についても言及すると良いです。
4. 労務計画
- 労務計画について詳しく説明します。そして必要な作業員の数や、作業員の配置、技能や資格のある作業員の確保方法について述べます。
- 労働力の不足を防ぐための予防策や、労働時間の管理についても触れると良いでしょう。
5. 安全計画
- 安全管理計画について詳細に記述します。安全対策として、どのような措置を講じたか(例: 安全教育の実施、安全設備の設置、現場の安全パトロールなど)を具体的に説明します。
- 特に、施工計画の段階でどのようにしてリスクを予測し、さらにリスクに対応する計画を立てたかについて触れます。
6. 品質管理計画
- 品質管理計画についての記述も重要です。施工計画に基づいてどのように品質を確保するか、具体的な検査方法や品質基準について説明します。
- どの段階でどのような品質チェックを行うか、また、万一問題が発生した場合の対応策についても記述します。
7. 環境対策
- 環境対策の計画についても触れます。そして施工が周囲の環境に与える影響を最小限に抑えるために、どのような対策を講じたかを具体的に説明します。
- 例えば、騒音や振動の対策、排水や廃棄物の管理、近隣住民への配慮などが挙げられます。
8. 施工計画の調整と変更対応
- 施工計画の調整や、計画変更が必要になった場合の対応策について記述します。例えば、天候や予期しないトラブルによる計画変更の対応方法や、変更に伴う他の工程への影響をどのように最小限に抑えたかを説明します。
- 計画変更時のコミュニケーションや情報共有の方法についても触れると良いでしょう。
9. コミュニケーション計画
- 施工計画の進捗や問題点を現場の関係者とどのように共有したか、さらにコミュニケーションの取り方や情報伝達の仕組みについて説明します。
- 定期的なミーティングや、関係者間の報告ルートの設定、緊急時の連絡体制など、具体的なコミュニケーション計画を記述します。
10. リスク管理
- リスク管理計画について説明します。施工中に発生しうるリスク(天候、資材不足、作業遅延など)を予測し、そしてそれに対する事前の対策や、リスクが発生した際の対応策を具体的に述べます。
11. PDCAサイクルの実施
- 計画段階での**PDCAサイクル(計画・実行・確認・改善)**の導入について記述します。そして計画を実施した後に、どのようにしてその結果を評価し、次回の計画に反映させるかを説明します。
12. 法令・規格の遵守
- 施工計画において関連する法令や規格をどのように遵守したかについて記述します。特に、安全や品質に関わる規定について触れることで、計画の信頼性を示します。
問題3
工期を守る為の工程管理上、留意した事項及びその理由を上げ、
それぞれに対して、具体的な対策又は処置を3つ記述しなさい。
留意事項:鉄骨製作、建て方の工程に留意した。
理由:他社物件と重なり製作段階での工程の遅れが予想されたから
具体的な対策又は処置
| ① | 良くない書き方 | 既製品のH形鋼を使用し、出来るだけ溶接作業を少なくし、現場溶接に切り替えた。 |
| 良い書き方 | 既製品のH形鋼を使用し、出来るだけ溶接作業を少なくした。 | |
| ② | 良くない書き方 | 1柱3階分の鉄骨を先行建て方とし、3階までコンクリート打ちをして製作期間を確保した。 |
| 良い書き方 | トラッククレーンを2台セットして地組みを多くし本締め足場も地組みし工程の短縮を図った。 | |
| ③ | 良くない書き方 | 上部の鉄骨建て方はパワーリーチで3階の床上で実施し、主体はトラッククレーンを用いた。 |
| 良い書き方 | 頂上部鉄骨にデッキプレートとシートで防雨して雨天での本締めと他の作業を実施した。 |
辻褄が合うように、リアルさを感じる施工経験記述の書き方にすること。
実際に施工管理技士になった気分で書きましょう。
問題4
工期を守る為の工程管理上、留意した事項及びその理由を上げ、
それぞれに対して、具体的な対策又は処置を3つ記述しなさい。
留意事項:ALC版取付け仕上げ工程に留意
理由:冬季で気温低下によるシーリング及び塗装工事の中断が予想されたから
具体的な対策又は処置
| ① | 良くない書き方 | ALCパネルの取付けは、人数を増やしてレッカー車を多用して取付けた。 |
| 良い書き方 | ALCパネルの取付けは1組3人グループを4組投入し、ALCの荷揚げにレッカーを使用した。 | |
| ② | 良くない書き方 | 午前10時頃から午後3時頃までの暖かい時間を使ってシーリング作業を実施した。 |
| 良い書き方 | 外部足場を各面で仕切り上部を密閉して内部をヒーターで暖めてシーリング作業を実施した。 | |
| ③ | 良くない書き方 | 外壁ALCは工場で吹付け塗装を行い、仕上げ塗装は、ゴンドラで温風器を使用して仕上げた。 |
| 良い書き方 | 外壁ALCは工場で吹付け塗装を行い、補修はゴンドラで温風器を用いて実施した。 |
1. 工期の設定とその根拠
- 工期の設定がどのように行われたか、その根拠を明確に説明します。例えば、設計段階でのスケジュール、契約上の納期、現場の条件などを考慮して工期を設定したことを記述します。
2. 工程表の作成と使用
- 工程管理の中心となる工程表について詳しく記述します。具体的には、工程表をどのように作成し、どのようにして現場で使用したかを説明します。
- どの工程がクリティカルパスとなっているか、つまり工期全体に大きな影響を与える重要な工程を特定し、その管理方法について述べます。
3. 進捗管理
- 進捗状況の把握と、それをもとにした工程調整の方法について記述します。また、定期的な進捗確認や、工程表に基づいたチェックを行い、遅れが発生しそうな場合にどのように対応したかを説明します。
- 進捗に問題が生じた際の対策や、事前に行った予防策についても触れると良いでしょう。
4. 作業員とリソースの管理
- 作業員の配置計画や、必要な資材・機材の手配と管理について記述します。例えば、リソース不足による工程遅延を防ぐために、どのように作業員を配置し、必要な資材や機材を確保したかを説明します。
- 特に、繁忙期や天候の影響を受けやすい時期におけるリソース管理について触れると良いでしょう。
5. 外部要因への対応
- 天候、災害、近隣住民からの苦情など、外部要因が工期に与える影響を考慮した管理方法について記述します。そしてこれらの外部要因に対する対応策を事前に計画し、工程に反映させたかを説明します。
- また、予期しない事態が発生した場合に、どのように迅速に対応し、工期を守るための対策を講じたかについても触れます。
6. コミュニケーションと調整
- 工程管理におけるコミュニケーションの重要性について説明します。さらに各工種間の連携、サプライヤーとの調整、定期的なミーティングを通じて、工事の進行状況を共有し、問題が発生した際の迅速な対応を可能にしたかを記述します。
- 関係者との情報共有や、現場でのリアルタイムな調整の方法についても触れると良いでしょう。
7. 工程変更への対応
- 計画段階では予測できなかった要因で工程が変更された場合の対応方法について説明します。例えば、工程変更が必要になった際に、他の工程や工期全体にどのように影響を与えたか、その影響を最小限に抑えるためにどのように対応したかを記述します。
- 工程変更後の再調整や、新たな工程表の作成についても触れます。
8. リスク管理
- 工期に影響を与えるリスクの予測と、そのリスクを管理するための具体的な方法について記述します。例えば、悪天候による工期遅延リスクに対してどのように対応したかや、資材の遅延リスクに備えた対策をどのように行ったかを説明します。
9. 振り返りと改善策
- 工期を守るために行った工程管理の結果を振り返り、成功した点や改善が必要な点について記述します。そして、次のプロジェクトに活かせる教訓や改善策を述べると、より具体的で実践的な記述になります。
10. コストとのバランス
- 工期を守るための工程管理がコスト管理とどのようにバランスをとったかについても触れます。また、工期短縮のためにどのような追加コストが発生したか、そのコストをどのように管理したかについて説明します。
問題5
作業所内の安全衛生体制又は活動上、留意した事項及びその理由をあげ、
具体的な対策又は処置を3つ記述しなさい。
留意事項:毎朝実施する常会の進め方に留意した。
理由:仕上げ作業に入って業者が増加し
毎日の常会の課題・進め方にバラツキが生じない為。
具体的な対策又は処置
| ① | 良くない書き方 | 常会とラジオ体操は必ず実施し、その日の作業内容を元請側が指示した。 |
| 良い書き方 | 常会は7時45分~8時15分とし、始め15分は作業指示確認とし、連絡事項を挟みラジオ体操を実施した。 | |
| ② | 良くない書き方 | 体操終了後、元請工事係立会いによるKYKの注意事項が読み上げられて注意を受けた。 |
| 良い書き方 | 体操終了後、業種・業者担当社員立会いによる現場でのKYKを実施した。 | |
| ③ | 良くない書き方 | 業者からの書類の提出を経て新規入場者への健康確認等を実施した。 |
| 良い書き方 | 業者からの書類の提出を経て新規入場者教育と高齢者作業員の健康確認を実施した。 |
あくまでも一級建築施工管理技士としての立場での記述とすること。
採点者に好まれるような内容としましょう。
問題6
作業所内の安全衛生体制又は活動上、留意した事項及びその理由をあげ、
具体的な対策又は処置を3つ記述しなさい。
留意事項:不安全箇所の是正方法に留意した。
理由:是正の時期が遅いと災害の発生の恐れが生じる為。
具体的な対策又は処置
| ① | 良くない書き方 | 不安全箇所を発見すると直ちに元請安全担当の連絡する方法が義務付けられた。 |
| 良い書き方 | 不安全箇所がわかっていながら自分達の業務でないなどの理由で是正しないので、是正隊を編成した。 | |
| ② | 良くない書き方 | 専門工事業者の当番制で毎日定時に安全巡回を実施する体制を作った。 |
| 良い書き方 | 構内電話から隊に連絡が入ると直ちに鳶職と業者の安全担当者を参加させ危険箇所を是正した。 | |
| ③ | 良くない書き方 | 不安全箇所は直ちに直された。また是正されていない箇所は気づいた人が直ぐ連絡した。 |
| 良い書き方 | 是正箇所を記録し何故発生したのか午後の集会で原因と対策を検討し午後の施工に生かした。 |
1. 安全衛生体制の概要を明確に
- 作業所内の安全衛生体制の全体像を簡潔に説明します。つまり、具体的には、安全管理の組織構成、安全衛生責任者の役割、定期的な安全ミーティングの実施など、全体の体制を概観します。
2. 具体的な安全衛生活動を詳細に記述
- 具体的な活動内容を詳しく記述します。例えば、安全パトロール、リスクアセスメント、安全教育、作業員への注意喚起、保護具の使用徹底など、日常的に行っている活動について説明します。
3. 留意した事項の選定理由
- なぜ特定の安全衛生事項に特に留意したのか、その理由を明確に記述します。例えば、過去に類似の現場で事故が発生した経験がある場合、それを防ぐために特定の対策に力を入れたというように、理由を具体的に説明します。
4. 安全衛生体制の成果や効果
- 設定した安全衛生体制や活動がどのような成果をもたらしたかを記述します。具体的には、事故の発生がゼロであった、ヒヤリハットが減少した、そして作業員の安全意識が向上したなど、実際の効果を具体的に示します。
5. リスクアセスメントの実施
- リスクアセスメントをどのように実施し、その結果に基づいてどのような対策を講じたかについて記述します。例えば、作業中の転落リスクを評価し、安全ネットの設置や作業手順の変更を行ったといった具体例を挙げます。
6. 緊急時の対応策
- 緊急時に備えた対応策についても触れます。例えば、火災や災害が発生した際の避難訓練の実施、救急用品の配置、緊急連絡網の確立など、万一の事態に備えた準備について記述します。
7. コミュニケーションと情報共有
- 安全衛生に関するコミュニケーションの取り方や情報共有の方法についても記述します。例えば、安全ミーティングの開催頻度、作業員からのフィードバックの取り入れ方、安全情報の掲示方法などを説明します。
- 作業員全員が安全に対する意識を共有し、さらに情報が迅速に伝わるような仕組みをどう構築したかを具体的に述べます。
8. 安全教育と訓練の実施
- 安全教育や訓練の実施状況について詳細に記述します。どのような内容の教育を行い、どのようにして作業員の安全意識を高めたか、教育の実施頻度や内容の更新についても説明します。
- 新規作業員への入場教育や、既存作業員に対する再教育の内容とその成果についても触れると良いです。
9. 法令遵守と規範の実施
- 法令や規範の遵守についても説明します。そして、関連する法律や規制に基づいた安全衛生管理がどのように行われているか、法令遵守の確認方法や、そのために行った具体的な取り組みについて記述します。
10. 安全衛生体制の改善点と対応
- 体制の改善点や、その改善策についても記述します。例えば、安全衛生活動を実施した結果として見つかった問題点や、改善が必要だった部分について説明し、それに対する対応策や改善の取り組みについて述べます。
11. 作業環境の整備
- 作業環境を安全かつ快適に保つための整備についても触れます。例えば、作業場所の清掃や整理整頓、適切な作業台の設置、作業区域の明確化など、作業環境の安全性を確保するための具体的な取り組みについて説明します。
12. 労働者の健康管理
- 労働者の健康管理についても記述します。そして、定期的な健康診断の実施、作業中の疲労や体調不良への対応、作業環境が健康に与える影響への対策について述べます。
問題7
躯体工事における品質管理上、留意した事項を上げ、
それぞれに対して、具体的な対策又は処置を3つ記述しなさい。
留意事項:プラントまでの距離があり、
交通渋滞も多いため生コンクリートの品質管理に留意した。
具体的な対策又は処置
| ① | 良くない書き方 | 早朝打設としてポンプ車を2台横付けして1時間80㎥打設する計画で生コン車を配車した。 |
| 良い書き方 | 近隣の了解を得て朝5時から打設し練り始めから90分以内に打ち終えた。 | |
| ② | 良くない書き方 | 早朝に1回ポンプ車の筒先で空気量、スランプ試験を行った。 |
| 良い書き方 | 午前と午後150㎥ごとに1回ポンプ車の筒先で空気量、スランプ塩化物を検査確認した。 | |
| ③ | 良くない書き方 | 特にスランプを重視して品質管理を実施し、流動化剤入りコンクリートとした。 |
| 良い書き方 | 空気量は4.5±1.5%、スランプは18±2.5cm、試薬で塩化物測定し、全て許容値以内を確 認した。 |
中途半端な数字を使うと逆に減点の対象となる。
2段構えで数字を使うと間違いない。
問題8
躯体工事における品質管理上、留意した事項を上げ、
それぞれに対して、具体的な対策又は処置を3つ記述しなさい。
留意事項 :天候が悪く工期が遅れがちで鉄筋ガス圧接作業の遅れに伴い
工事が雑になる恐れがあるためガス圧接作業、かぶり厚さに留意した。
具体的な対策又は処置
| ① | 良くない書き方 | 圧接面の加工状態、圧接後の状況を巡回して目視検査した。 |
| 良い書き方 | 圧接面の加工状態、圧接後の目視検査、かぶり厚さを重点に全数の鉄筋工事を目視検査した。 | |
| ② | 良くない書き方 | 圧接のふくらみや軸の編心については、所定の基準値を合格として検査した。 |
| 良い書き方 | 圧接のふくらみ1.4d以上、軸の編心0.2d以内を合格とし鉄筋全ての超音波探傷検査を実施した。 | |
| ③ | 良くない書き方 | 柱、梁、耐力壁のかぶり厚さ、またスラブについても所定のかぶり厚さを検査確認した。 |
| 良い書き方 | 柱、梁、耐力壁で外部側のかぶり厚さは50㍉、屋内側は40㍉を全て確保確認した。 |
1. 躯体工事の品質管理の目的
- 躯体工事における品質管理の目的を明確に記述します。例えば、構造物の強度や耐久性を確保し、施工後の問題を未然に防ぐための品質管理がどのように行われたかを説明します。
2. 施工計画と設計図面の確認
- 施工計画や設計図面に基づく品質管理の重要性について説明します。そして、設計図面の確認、施工計画に対する理解と、それに基づく施工の適正性を確保するためにどのような取り組みを行ったかを記述します。
3. 材料の品質管理
- 使用する材料の品質管理について記述します。例えば、コンクリート、鉄筋、型枠などの材料が設計仕様に合致しているか、材料の検査や試験をどのように行ったか、材料の保管方法や取り扱いに関する管理をどのように行ったかを説明します。
- 材料の品質不良が発覚した場合の対処方法や、品質を確保するための検査の頻度についても触れます。
4. 施工中の品質チェック
- 施工中の品質チェックの実施状況について具体的に説明します。例えば、コンクリートの打設時の管理、鉄筋の位置や間隔の確認、型枠の設置状態の検査など、施工中に行った具体的なチェック項目とその結果について述べます。
- 定期的な点検や、チェックリストを用いた品質確認方法についても説明します。
5. 施工精度の確保
- 施工精度の確保に関する取り組みを記述します。例えば、鉄筋の位置決め、型枠の設置精度、コンクリートの打設高さの管理など、施工精度を保つために実施した具体的な対策や方法について説明します。
6. 品質管理に関する問題発生時の対応
- 品質管理中に問題が発生した場合の対応について詳しく記述します。そして、問題が発生した際にどのように対処し、再発防止策を講じたか、問題解決のためにどのような改善策を実施したかを説明します。
- 例えば、施工ミスや材料不良が発生した場合の補修方法、工程の見直しについて触れます。
7. 検査・試験の実施と記録
- 検査や試験の実施について具体的に説明します。そして、コンクリートの圧縮強度試験、鉄筋の引張試験など、品質確認のために実施した試験の内容とその結果について述べます。
- 検査や試験の結果の記録と管理についても触れ、どのように結果を文書化し、後に参照できるように管理しているかを説明します。
8. 法令や規格の遵守
- 法令や規格の遵守についても記述します。さらに関連する建築基準法や施工規格に基づいた品質管理がどのように行われているかを説明し、法令遵守の確認方法やその結果について触れます。
9. 施工管理者や作業員への指導
- 施工管理者や作業員に対する品質管理の指導方法について記述します。例えば、品質に関する教育やトレーニングをどのように実施したか、作業員に対して品質管理の重要性をどのように伝えたかを説明します。
10. 品質管理の改善と振り返り
- 品質管理の改善点や振り返りについても触れます。そして、施工後の振り返りを通じて見つかった改善点、次回の施工に向けた改善策について述べ、品質管理の向上にどう繋げたかを記述します。
✨✨✨ LINE限定で記述用テンプレを無料配布中!✨✨✨

令和8年度版のオリジナル参考書が完成しました!
手元に参考書が欲しいという方は下記サイトで販売をしています。
A4用紙で238枚分というかなり濃い内容となっています。
※参考書には、このサイトに掲載がされていない情報も沢山載っています。
どこでご購入をされても内容は同じです。
『一級建築施工管理技士』で検索をして下記の画像を探してください!
📩 商品の直接購入をご希望の方は、[こちらのフォーム]からお問い合わせください。
お急ぎの方はデータでの販売も行っています。
※ご購入にはPayPalアカウントが必要です。まだお持ちでない方は、事前に無料登録をお願いいたします。
Paypalの新規登録・利用(無料)はこちら⇒ Paypal公式サイト
掲載内容
1.出題の見直し2年目で出題のパターンが見えた?
令和6年度から記述問題の出題形式が見直され、過去2回の試験を経て、令和8年度で3年目を迎えます。この2年間の出題傾向から、一定のパターンや対策の方向性が見えてきました。本書では、それらの傾向をふまえ、令和8年度に向けた記述対策のポイントを整理しています。
2.過去20年の出題傾向
年度ごとに詳細をまとめました。これをじっくりと分析することで、これまでの流れが見えてくるはずです。さらに、その流れを読み解けば、次年度にどのようなテーマが出題されやすいのかを予測する手がかりになるかもしれません。
3.平成18年度~令和7年度の本試験解答例
試験対策として過去問を理解することは基本です。そして、令和6年度に第二次検定の見直しが実施されましたがそれでも過去問を捨てることは出来ません。繰り返し見ていると、どういうところが設問として出やすいのか見えてくると思います。そして、2年目で試験の傾向が見えたことから、令和7年度からの解答例数を大幅に増やしました。これに勝る試験対策はありません。
4.構造種別 経験記述例
新築工事において特に重要な、主要構造の3種類(鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造)に関する施工例を豊富に取り揃えています。さらに「おまけ」として、新築工事だけでなく改修工事に関する施工例も追加しました。
5.業種別 重点対策問題
受検者には、専門工事業の方が多い現実を踏まえ、この参考書では全17業種にわたる解答例を準備しました。そして、実際の施工現場を想定した具体的で実践的な内容により、各業種ごとの特徴を踏まえた解答を分かりやすく解説しています。
6.一問一答式
試験対策に役立つ解答の「引き出し」として、知識を効率よく整理できる一問一答形式の内容を加えました。そして、この形式では、試験で問われやすい内容を厳選し、要点を簡潔にまとめています。忙しい受検者の方でも、スキマ時間を活用して効率的に学べる工夫を盛り込んでいます。
7.良い記述例・良くない記述例
同じ内容でも、記述の仕方一つで採点者に与える印象が大きく変わります。さらにこの章では、採点者の視点を意識した「良い記述例」と「良くない記述例」を比較しながら、効果的な表現方法を学ぶことができます。
8.施工経験記述はこの3つ!
施工経験記述の出題傾向を分析した結果、対策すべき課題は3つに絞ることができます。そして、これら3つのテーマごとに、出題ごとの解答の注意点や重要な記述のポイントをまとめています。この章を読み込むことで、施工経験記述の対策は万全です。
9.令和8年度予想問題 鉄骨(S)造・鉄筋コンクリート(RC)造
令和6年度は「鉄筋コンクリート(RC)造の合理化」、令和7年度は「鉄骨(S)造の品質管理」でした。この章では鉄筋コンクリート(RC)造、鉄骨(S)造での品質管理・合理化・環境管理それぞれ6パターンでの設問と解答例を考えてみました。ヤマを張ることはオススメ致しません、しかし対策は必要です。
過去問データからの施工経験記述対策
- 出題の見直し2年目で出題のパターンが見えた?
- 過去20年の出題傾向
- 施工経験記述 過去19年分の本試験解答例
- 構造種別 施工経験記述例
- 業種別 重点対策問題
- 施工経験記述 解答参考例
- 応用問題が出ても怖くない!一問一答式で対策
- 建設副産物・環境問題への対策から経験記述を考える
- 施工経験記述の良い書き方・良くない書き方
- 独学でも出来る!施工経験記述はこの3つ!
記述対策に活かせる実例・体験まとめ
応援サポート教材(有料)
最新の施工経験記述対策メニュー
1.鉄骨造パターン
2.鉄筋コンクリート造パターン
二次試験へ向けて有効活用致しましょう♪
市販の参考書も加えるとより効果的!