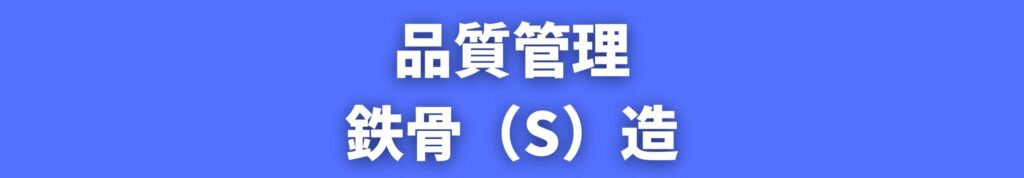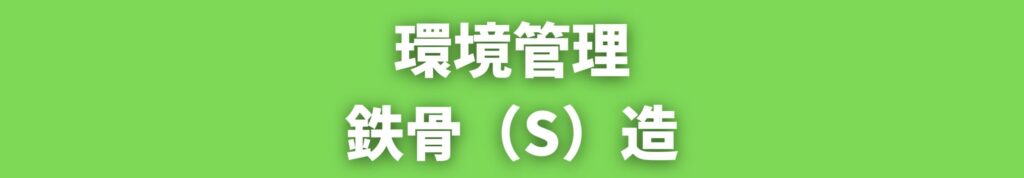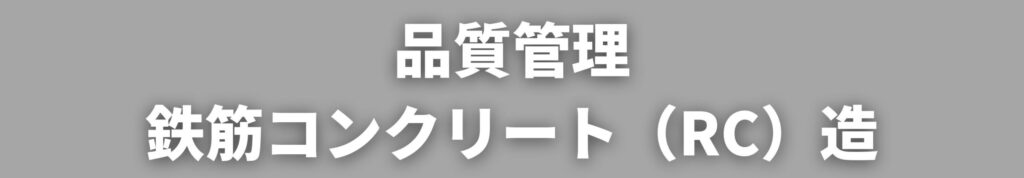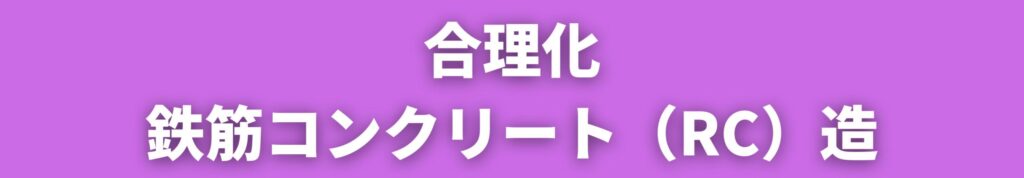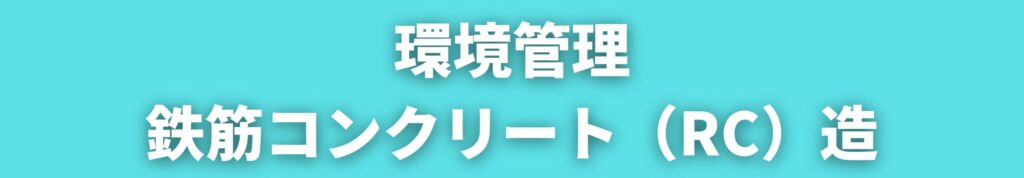一発合格に向かって
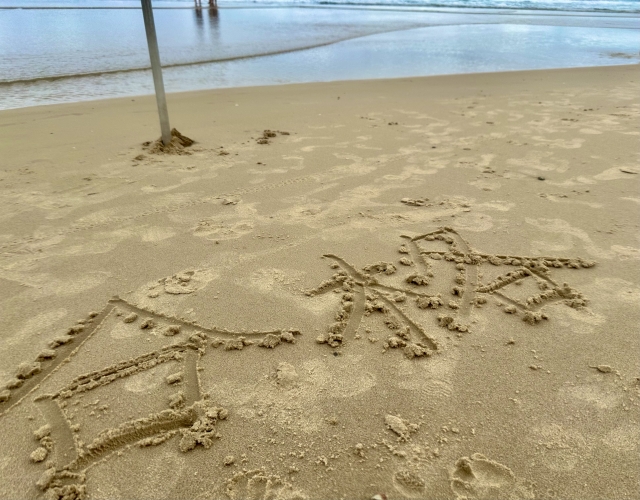
一級建築施工管理技士の施工経験記述の準備は早ければ早いほど良いかと思います。
ただ、最初から力を入れすぎると息切れをしてしまいます。
なので、ゆっくりと進めていくが良いでしょう。
さらに、第一次検定と第二次検定はリンクをしています。だから、第一次検定の時から第二次検定を意識をした学習をする方が良いかと思います。そして、最終的には自分なりのパターン(解答例)を作り上げて試験に臨みましょう。
学習方法及び注意点
施工経験記述は、一級建築施工管理技士の第二次検定において非常に重要な要素です。そのため、この部分をしっかり対策することで、合否に大きな影響を与える可能性があります。以下の点に注意して学習することで、より高品質な施工経験記述を作成できるようになります。
1. 経験の整理と論理的な構成
施工経験を整理し、論理的に説明することが重要です。「計画 → 実施 → 結果」の流れで書くと分かりやすくなります。計画では課題、実施では対策や工夫、結果では成果や改善を具体的に説明しましょう。
2. 課題解決能力を強調する
施工現場では予期せぬ問題が多発するため、その対策や改善策を明確に書くと評価されやすいです。特に、判断力や問題解決力が伝わるエピソードを選びましょう。
3. 具体的な数値やデータを活用する
説得力を高めるために、具体的な数値やデータを盛り込みましょう。工期短縮やコスト削減、安全対策の成果などを示すと、実績の裏付けになります。
4. 法律・規則や基準への適合を意識する
施工経験記述には、建設業法や労働安全衛生法などの法令や基準に準拠した内容を盛り込むことが求められます。法令や規則に従いながら、どのように適切な施工を行ったかを明示することで、信頼性の高い記述になります。
5. 第三者にもわかりやすく書く
試験官は現場を知らないため、簡潔で明確な文章を心がけましょう。専門用語を控え、具体的な事実や行動を伝えることが大切です。図や表が使える場合は活用しましょう。
6. 結果に対する自己評価を行う
最後に、施工経験の結果に対してどのように自己評価を行ったかを記述することも重要です。また、成功した点だけでなく、反省点や改善すべき部分があれば、そこも誠実に書くことで、自己改善意識が高いことをアピールできます。
7. 第三者の添削を受ける
自分で書いた内容は、どうしても主観的になりがちです。施工経験記述は、第三者に添削を依頼して客観的な視点からのアドバイスを受けると良いでしょう。特に試験に精通した人や、過去に実際に合格した人からのフィードバックは非常に有効です。
8. 過去の事例を参考にする
過去の合格者の施工経験記述を参考にすることで、どのような内容が評価されるのか、具体的なイメージが掴めます。あなたが販売している「リアルな添削を受けた資料」も大いに活用し、実際の事例に触れることで、質の高い記述を目指しましょう。
施工経験記述は、単なる作業の羅列ではなく、どのように現場を管理し、問題を解決して成果を出したかを的確に伝えるスキルが試される場です。しっかりと準備し、論理的で説得力のある内容に仕上げることが大切です。
令和7年度版のオリジナル参考書が完成しました!
手元に参考書が欲しいという方は下記サイトで販売をしています。
A4用紙で243枚分というかなり濃い内容となっています。
※参考書には、このサイトに掲載がされていない情報も沢山載っています。
どこでご購入をされても内容は同じです。
『一級建築施工管理技士』で検索をして下記の画像を探してください!
お急ぎの方はデータでの販売も行っています。
※すでにPayPalアカウントをお持ちか、新たにアカウントを開設された方に限ります。
Paypalの新規登録(無料)はこちら⇒ Paypal公式サイト
過去問データからの施工経験記述対策
- 過去19年の出題傾向
- 見直しで施工経験記述はどう変わった?
- 施工経験記述 過去18年分の本試験解答例
- 構造種別 施工経験記述例
- 業種別 重点対策問題
- 施工経験記述 解答参考例
- 応用問題が出ても怖くない!一問一答式で対策
- 建設副産物・環境問題への対策から経験記述を考える
- 施工経験記述の良い書き方・良くない書き方
- 独学でも出来る!施工経験記述はこの3つ!
最新の施工経験記述対策メニュー
1.鉄骨造パターン
2.鉄筋コンクリート造パターン
二次試験へ向けて有効活用致しましょう♪