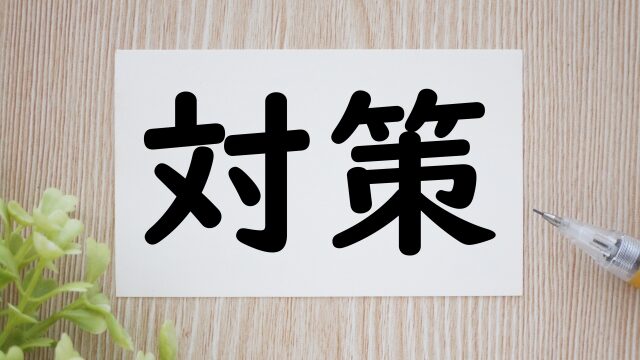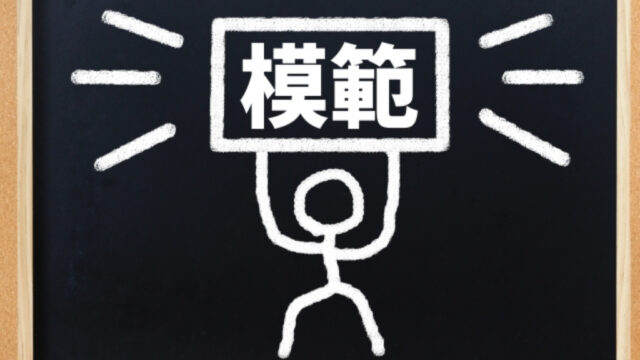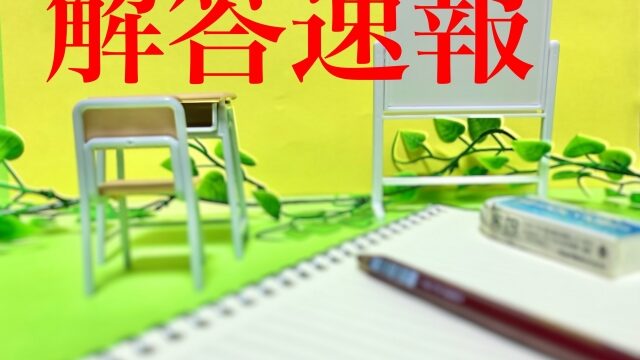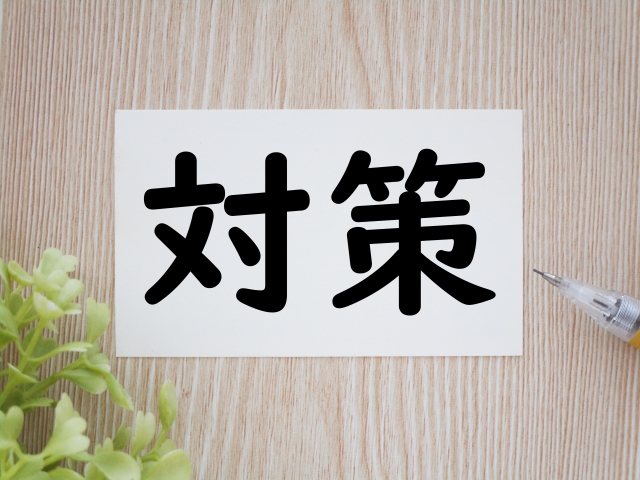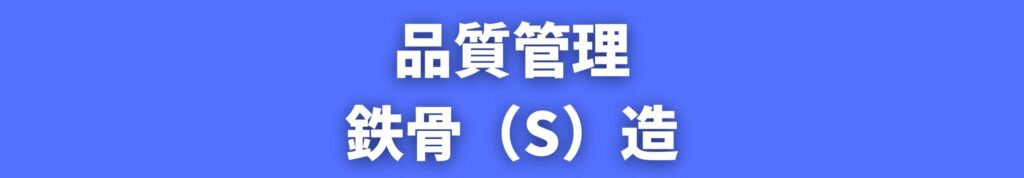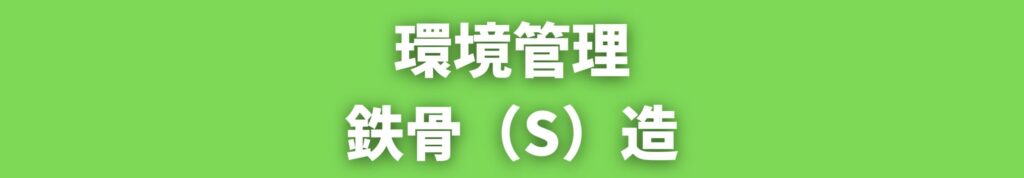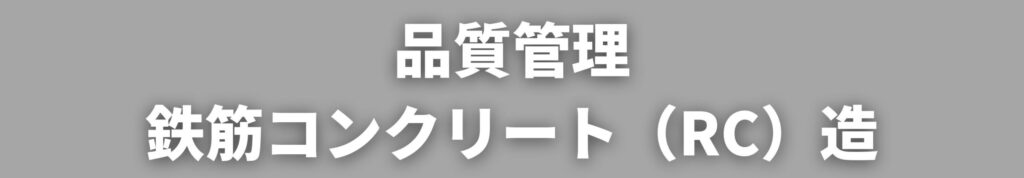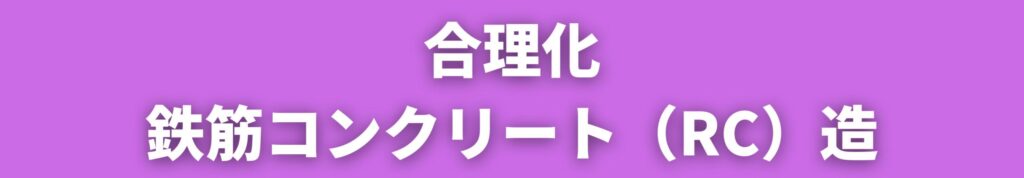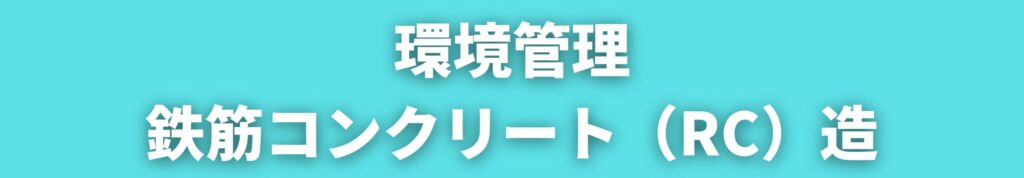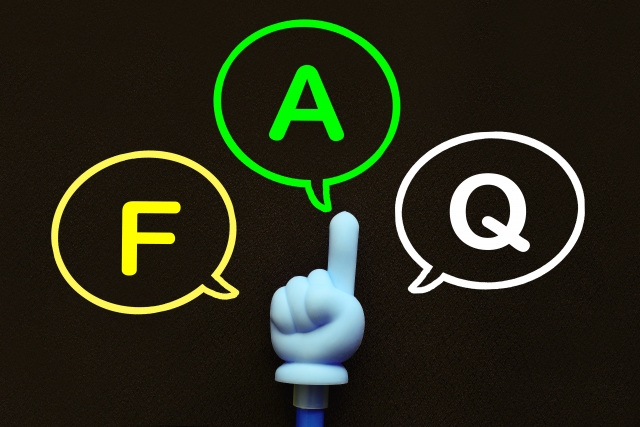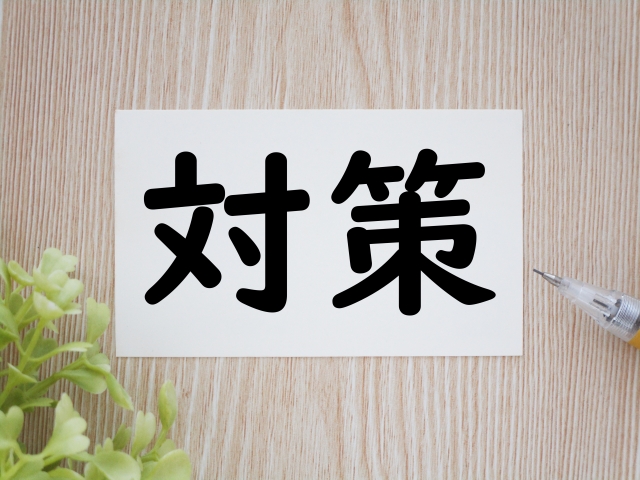
建設副産物や環境問題について
業界における副産物や環境問題に対処する方法はいくつかあります。
リサイクルと再利用
建設副産物や廃棄物をリサイクルして再利用することで、資源の浪費を減らし、廃棄物の処分量を削減できます。例えば、コンクリートの再利用や再生アスファルトの利用などが挙げられます。
省資源型建設
建設プロセスで使用する資源を削減することで、環境負荷を軽減できます。例えば、省エネ材料の使用や、省水型設備の導入などがあります。
環境に配慮した設計
建設プロジェクトの設計段階から環境に配慮した取り組みを行うことが重要です。例えば、エネルギー効率の高い建物設計や、自然環境への配慮を含んだ施設設計などが挙げられます。
排出物管理と処理
建設現場での排出物を管理し、適切に処理することが重要です。これには、廃棄物の分別や適切な処理方法の選定が含まれます。
技術革新とイノベーション
新技術やイノベーションを取り入れることで、環境への影響を軽減することが可能です。例えば、環境に配慮した建設材料の開発や、クリーンエネルギーを活用した建設プロセスの導入などがあります。
これらの対策を総合的に取り入れることで、建設業界の副産物や環境問題に対処することができます。
コンクリート

| 留意事項 | コンクリートガラ 場所打ち杭の杭頭処理時に発生したコンクリートガラ 旧地中梁残材(コンクリートくず) 撤去コンクリートガラ 存建物を解体した際のコンクリートガラ コンクリートのテストピースで余ったもの |
| 処置対策 | 杭頭処理で発生したコンクリートガラを仮設通路に敷きつめた。 コンクリートガラをクラッシャーで砕き、場内仮設路、駐車場にまいた。 細かく砕いて、砕石にして仮設路に敷いた。 コンクリートは、取壊し後、破砕して現場内搬入路路盤に使用した。残材は、近くの処理施設に運搬処分した。 根切り時に地中より出てきた旧機械基礎のコンクリートガラを、現場にてクラッシャー処理し、仮設道路の路盤材として使用した。 既設基礎の解体に伴い発生したコンクリート塊は、鉄筋とコンクリートに分け、さらに細砕して道路に敷いた。 既存建築物を解体した際に発生したコンクリートガラを敷地内通路に敷き、工事 車両・重機の進入を容易にした。 コンクリートガラの発生を抑制するため、型枠建込み~コンクリート打設に至る一連の工程を入念にチェックリストに基づき管理し、はつり等の手戻り作業をなくした。 現場内の解体作業で発生したコンクリートガラを簡易プラントで砕き、軟弱な場内仮設道路の路盤材として使用した。 発生したコンクリートガラを仮設通路の路盤として使用した。 アースドリル杭の余盛り部分のコンクリートを壊し、中央部の強度のあるコンクリート塊を耐圧盤の地業工事資材として再利用した。 コンクリートガラをクラッシャーで砕き場内仮設路に敷いた。 根切り時に発生した旧地中梁の撤去に伴うコンクリートくずをコンクリート再生プラントへ持ち込み処分した。 撤去したコンクリートガラを再生処理し、躯体コンクリートの骨材として再利用した。 既存焼却施設の解体に伴って発生したコンクリートガラを再生処理して基礎工事 に使用した。 解体作業によって発生したコンクリート殻を現場で小割にし、仮設進入路の路盤材とした。 コンクリートガラを現場に設置した簡易プラントで再生砕石とし、基礎下に敷いた。 生コン打設時の残りコンクリートを極少にした。 コンクリートガラを細分化して仮設通路の鉄板の下に敷き再利用した。 現場から発生したコンクリートガラを粉砕し、再生クラッシャーランとして駐車場の路盤材として使用した。 花ダンの縁石として利用する。 砕石として利用する。 アスファルト舗装の材料として使用する。 |
| 結果評価 | 仮設道路のトラフィカビリティが向上し、安全な車両通行ができた。 ダンプ等が安全に走行でき、作業員の車も場外へ泥を持ち出さず、近隣道路もきれいであった。 車両の走行がスムーズにできたため、ダンプの向上性がアップした。また、砕石を購入しなくてもよくなり、コスト削減ができた。 現場で生じたものを現場内で処理したので、有効利用できた。 仮設道路の路盤材として、強度的に問題なく使用できた。路盤材料購入費が約 30%削減でき、今後も採用したいと考える。 泥のはね上がりが減少し、車の通行に際し、ほこりも少なく安全に運行できた。 進入路地固めの砕石購入料が減り、また重機の転倒防止ができ、安全に工事を進められた。 はつり等の手戻りをなくすことにより、建設廃棄物の発生を抑制することができた。 また、余分な作業も回避できた。このことにより、コスト面、品質面、環境面において効果があった。 砕石の購入費用を抑えることとなり、また、産業廃棄物処分費も大幅に削減することができた。 車両・重機の走行に問題なく、仮設費用の低減となった。 購入する資材の削減ができた。砕石と混合し、良い堅固な地業工事を構成することにつながった。 場内仮設路のトラフィカビリティーが向上し、ダンプ及びクローラーが安全に走行できた。砕石敷きの材料費、杭頭処理残材廃棄処理費が約 50万円節約できた。 循環資源を再生砕石、再生骨材として再生利用でき、処理代、コンクリート及び砕石購入節約できた。循環型社会の形成推進に貢献できた。 必要な強度も確保され、建設副産物の発生抑制にもつながった。環境保全の観点からも採用していくべきである。 産廃処分費用より再生処理費用のコストの方が安くなるため、コスト削減が可能となった。再生資源活用の当初目標 10%が達成できた。 工事車両もスムーズに搬入出でき、合理的に現場を進められたが、小割にするのに予想以上に日程を費やした。合理的に現場作業を進めることができた。 砕石購入の費用が不要になり、副産物を処理する手間が削減できた。今後も積極的に活用すべきと考える。 生コン打設前に打設順、人員計画、数量を明確にし、残コンを少なくした。事前に計画通り施工できたので残コンがなくなった。 砕石を購入予定だったが、資源の節約ができた。次回は細分化の方法を検討する必要がある。 中間処理場までの運搬費等がかかったが、再生利用材として現場から発生したものを又現場に戻すことができた。コンクリートガラの再生利用が可能になった。 |
ガラ:コンクリートの廃材や破片を指す用語
杭頭:地中に打ち込まれた杭の地表面に近い部分
根切り:基礎工事のために地盤を掘削する作業のこと
トラフィカビリティ:地面の交通可能性や車両の通行に適した状態を指す用語
中間処理場:廃棄物を最終処分する前に一時的に集積・処理する施設
梱包材

| 留意事項 | 包装材・梱包材 タイル材の梱包材 資材の梱包用ダンボール 仕上げ材の梱包材 資材等の梱包材 アルミニウム製建具の製品養生材 (エタフォーム ) 包装用ダンボール |
| 処置対策 | 搬入材料の包装材等を仕上げの養生材として使用した。 協力業者へ要請し、パレット等による搬入とした。 資材の梱包用ダンボールを仕上げ材の養生材として使用した。 関係業者に、梱包を少なくすると同時に、材料そのものを再使用するために引き取ってもらった。 包装の簡略化及び無梱包搬入となるよう工夫した。 作業員に分別収集を徹底させ、一般ごみと区別し、古紙回収業者に引取りしてもらった。 あらかじめ資材搬入業者に依頼し、梱包材の少ないものを選定し、パレット等による搬入を促進した。 メーカーに依頼して、再利用できる梱包材を使用した。 各種仕上げ材の梱包材の削減を協力会社、メーカーに要請し、パレット等による搬入を促進した。 全工種に対して廃棄物の処理方法について指導を徹底して行い、分別化を図った。 梱包材の少ない材料を選んだ。また材料メーカーに梱包材を削減するように指示した。 アルミニウム製建具の数が多いため、枠の四端の養生材を簡易養生で搬入することとした。 仕上げ部分の養生材として使用し、その後再生紙原料として処分業者へ委託した。 |
| 結果評価 | 包装材の処分費が減り、養生代を削減できた。 梱包材の量を減らすことができた。 養生材の購入費が約 15%削減できた。完成後にはリサイクル業者に持ち込んだ。今後も検討していきたいと考える。 木材の残ガラがほとんどなく、環境面から良い結果となった。 紙くずの仕分け作業が減るとともに、廃棄物の減少につながった。 作業員のごみの分別回収の意識高揚・作業場内の整理整頓にもつながり、作業性が向上した。 現場搬入材料の無梱包化の促進によって梱包材を大幅に削減でき、産業廃棄物の処分費用を削減できた。 現場で処理するごみが減り、現場の美化にもつながった。 これまでに比べて搬出される梱包材の量を約 20%削減することができた。 指導を徹底したことにより処分に関する建築コストが従来に比べ 15%以上削減できた。 建設副産物が抑制でき、コストダウンにもつながり、満足できる成果であった。 ゴミが減り整理整頓にもつながるとともに、工程も順調に進んだ。現場の美化と作業工程の短縮に貢献できた。 現場で発生する養生材を約半分とすることができ、大幅に養生材のゴミが減った。他の工種でも実施することで一層抑制につながる。 |
型枠

| 留意事項 | 1Fスラブ型枠 鋼製型枠 型枠材 (せき板 ) 型枠材料残材 (木くず ) コンクリートスラブの型枠 木製型枠 |
| 処置対策 | スラブ型枠をフラットデッキに変更した。 型枠材を合板からプラスチック型枠へ変更した。 2Fデッキには鋼製型枠を使用することにし、木くずの発生を抑えることを実施した。 施工図作成時から他部所で流用できる型枠寸法とし、木製型枠は使用せず、プラスチック型枠を使用した。 マンションであり躯体寸法が同寸のため、せき板を合板からプラスチック型枠へ変更した。 型枠加工に伴う大量の木くずの残材を現場に設置した産業廃棄物箱へ捨てずに、持ち込み業者に持ち帰らせた。 床版コンクリート打設にデッキプレートを使用した。 デッキプレートに変更した。 型枠を加工場で加工した。 RC造の各階の型枠材料を打設後、その他の階で使用できるように工夫して施工図を作成する。 建設発生木材を出さないために、鋼製型枠を使用した。 ウッドチップを使用したのり面保護の吹付け材を他の現場工事における遊歩道の 路面材に使用した。 |
| 結果評価 | 工期短縮及び型枠材料費の削減を行った。 合板の残材発生もなく、現場内もくぎ等が落ちていなく、安全できれいな現場となった。 木くずの発生抑制及び、型枠の現場加工の労務削減ができた。 流用寸法とすることで、型枠数量を少なくすることができ、残材処分量も少なく処分費も軽減できた。 15階建であったが、せき板を途中で交換することなくできた。合板せき板の残材発生もなく完工できた。 通常木くずは、産業廃棄物処理業者が回収に来るが、持ち帰らせることにより抑制効果も上がり処理代も節約できた。各業者廃棄物持ち帰りを徹底して、不用材持ち込みが減った。 型枠の処分が必要なくなり、建設副産物の発生の抑制だけでなく、工期短縮にもつながった。副産物の抑制のみならず、工期短縮も可能となるため今後も採用すべきである。 型枠 (天然資源である木材 )の使用量を減らし、工期短縮に貢献できた。環境保護には有効であると考える。 現場での加工を行わないので、ゴミが減り精度も確保できた。木材の省資源化に貢献できた。 天然資源である木材の使用を減らすことができて、環境保護にも役立った。 廃棄処分費の低減を行うことができた。 |
木材

| 留意事項 | 木材 寄木の養生材 設備機器の梱包材の木材 |
| 処置対策 | 養生紙を使用していたがプラスチックダンポールに変更し、他の現場で再使用した。 小さくカットして木材チップにし燃料として使用する。 チップ化し、木毛セメント板の材料として利用する。 |
石膏ボード

| 留意事項 | 石こうボード プラスターボード PC板 |
| 処置対策 | 廃材を分別回収するため、専用コンテナを設置して仕分けた。そしてメーカーに仕分けた廃材を再利用してもらった。 施工図でボードを割付けしロス材のないように努めた。 発生材の再利用のため、雨にぬれないよう、他の発生材が混合しないように区別して、シートで囲った。 廃材を分別回収しメーカーに再利用させた。 石こうボードは専用のコンテナを設置してそれに仕分け、ボードメーカーが引き取り再利用した。 石こうボードの切れ端等を再生工場へ持ち込み、リサイクルボ―ドとして使用する。 型枠の残材 (木材 )とコンクリートガラの発生を抑制するため、住戸内スラブ、廊下・バルコニースラブにハーフ PC板を使用することとした。 |
| 結果評価 | 再生利用することにより、石こうボードのごみも出なくなり、資源が再利用できた。 残材と廃材の量が減少し資材スペース内に納まり、作業時間も短縮できた。現場内がすっきりとし、作業スペースも広くとれ、作業効率がアップした。 雨にもぬれず汚れも防止できた。他の発生材も混入せず、再生利用のため搬出することができた。すべての発生材も同様に行うことで、現場内の美化が図れた。 現場の職方にも再生利用の考えが広まり、材料を大切に使うようになった。材料費が減り、コストダウンにつながった。 現場内では石こうボードとしてのゴミが全くなくなった。資源を 100%利用でき、再生利用に貢献できた。 木材とコンクリートガラの発生が抑えられ、結果的に支保工の使用量も少なくすみ、躯体工事の運搬車両も約 3割削減できた。 |
アスファルト

| 留意事項 | アスファルトガラ アスファルトコンクリート 再生舗装材の使用 再生アスファルト |
| 処置対策 | アスファルトガラは、小さく破砕後、マニフェスト管理にて処分場に運搬した。 駐車場解体時に発生したアスファルトガラをアスファルトプラントに持ち込み、再生アスファルトとして使用した。 施工前の現場がアスファルト舗装の現場で大量のアスファルトガラが発生し、再生処分を行う再生プラント工場に持ち込み引取りしてもらった。 アスファルト舗装撤去に伴うアスファルトガラをアスファルトプラントに持ち込み、再使用してもらうことで、合材を安く購入できた。 アスファルトを解体撤去後、アスファルトプラントに搬出し、再生アスファルトとして使用する。 現場駐車場の舗装材料を再生舗装材とした。 解体工事跡が駐車場となる場合に、現場で発生したコンクリートくずやアスファルトくずは、現場で再生し戻して施工する。 |
| 結果評価 | マニフェスト管理にて、確実に量的及び質的にも管理できた。 外構工事の駐車場の舗装時、プラントより安価で再生アスファルト合材を購入できた。コスト的に成功したと考える。 アスファルトガラを再生処分してもらい、建家周りの舗装材の再生骨材として再利用できた。 |
金属

| 留意事項 | 金属屑 鉄骨、鉄筋屑 |
| 処置対策 | 金属くずについては、量の多いとき処分業者に引き取らせ、また各専門業者に自己処分させた。また、ストックヤードに小分け区分した。 現場内において分別を徹底し、リサイクル可能な金属くずはスクラップ業者に有償で引き取らせた。 現場から発生する金属屑類を、鉄・ステン・アルミ・その他に分別集積を行い、専門業者に回収してもらった。 再生異形棒鋼 (SDR材 )の原料として処分業者へ委託した。 金属回収業者に再使用 (リユース工場処分 )を依頼するため、産業廃棄物箱を設置し金属別に分別を実施した。 鉄筋コンクリート撤去後、コンクリートガラ、鉄筋等を分別し再生処理後、再使用する。 溶融炉を採用しているごみ処理場へ持ち込み、舗装材料等へ再生する。 |
| 結果評価 | 専門業者に自己処分させることにより、現場内が清潔整頓され、それぞれの意識も高まった。 建設廃棄物としての処理費用を発生させず、コスト面、環境面において有効であった。 |
土砂

| 留意事項 | 建設発生土砂 |
| 処置対策 | 基礎掘削により発生した土砂は、敷地に余裕があったので一時貯蔵し、交通量の少ない土・日に搬出した。 当建設敷地内に、地業工事の際に発生した残土を埋戻し工事まで仮置きした。 現場で杭工事から発生した建設汚泥を天日乾燥及びセメント系固化剤による改良 を行う計画を立案し、発注者及び管轄行政環境部局の承認を得て、場内で埋戻し材として使用した。 現場で発生した残土は、社内の情報共有システムを活用し、他現場で利用するよう促進した。 建設発生土情報交換システムを使用して、土砂の搬出先を選定した。 埋戻し土は発生土を場内に仮置きして再利用することとし、ストック場所を確保するために、現場事務所は隣地を借りて設置した。 建設発生土の搬出にあたり、再生資源利用促進計画を作成し、再利用を推進した。 埋戻しに際し、他の現場で発生した建設発生土の利用を図った。 建設発生土に関する情報を広く周辺現場へ周知し、他の建設現場での利用を促進した。 不法投棄されないよう、捨て場の確認、立会いなど、管理を徹底した。 施工計画時点で、建設発生土や産業廃棄物が多くならないよう仮設計画を立案した。 |
| 結果評価 | トラックの輸送コストが減ったのと、交通量の少ない土・日に搬送することにより、安全に輸送できた。 仮置きすることにより、残土処分費用の軽減、工期の短縮をすることができた。 建設廃棄物として埋立て処分場へ搬出せず、場内にて再利用することで、コスト面、環境面で非常に有効であった。 搬出土の処分費と埋戻し土の入手費用を 3割程度削減することができた。土砂の工事間での有効利用ができた。 残土搬出車両が少なくすんだことで、近隣からの苦情や交通障害もなく、工程も予定より 1週間ほど短縮できた。 |
混合廃棄物

| 留意事項 | 混合廃棄物 |
| 処置対策 | 混合廃棄物の発生を抑制するため、建設リサイクル法対象品目以外でも、再利用化施設で処理できるものは分別収集することとした。 |
| 結果評価 | 発生量は当初予想の約 2割減となり、再資源化にも貢献できた。職員・作業員にも分別 の意識が浸透した。 |
タイル

| 留意事項 | 外壁小ロタイル エコタイルの使用 インターロッキング材等 |
| 処置対策 | 外壁タイル打込み、プレキャストコンクリート型枠にて外壁型枠を施工した。 施主、設計事務所に申し出てエコタイルの使用を行った。 現場で余ったインターロッキング等は地元住民たちのチャリテイバザーに提供し、産廃として出さないようにする。 |
| 結果評価 | タイル張りに伴う下地モルタル塗りから発生する余剰モルタルごみなどが減少し、タイル・型枠工事からの発生副産物は削減し目標どおりであった。 |
ALC

| 留意事項 | ALC版 |
| 処置対策 | ALC版を破砕し、再度粘土と混合し、細かい粒径に焼成し人工植土として利用した。 |
| 結果評価 | 庭園・築山の植土として利用でき、コスト削減につながった。 |
再生砕石

| 留意事項 | 再生砕石の利用 |
| 処置対策 | 基礎下、土間下に再生砕石の利用をうながした。 |
| 結果評価 | 設計事務所に地球環境の保全を申し出て利用することができた。再生砕石を利用したことによりリサイクルを果たせた。 |
ウレタン材

| 留意事項 | ウレタン材 (陸上競技場 ) |
| 処置対策 | ウレタン材撤去後、再生処理施設で再生ウレタン材として走路、屋上などに使用する。 |
瓦

| 留意事項 | 瓦 |
| 処置対策 | 解体工事等で発生する瓦を破砕機械で細かくし、整地などに砕石のかわりに使用する。 |
地下水

| 留意事項 | 地下水 |
| 処置対策 | 地下水をポンプで汲み上げ沈砂槽にかけてから、土工事の道路清掃に再利用した。 |
産業廃棄物

| 留意事項 | 産業廃棄物 |
| 処置対策 | 運搬及び処分を委託する場合、委託業者がその分野の登録業者であるかどうかに留意した。 委託業者へ産業廃棄物管理票を発行することに留意した。 適切な産業廃棄物収集業者と委託契約し、発生した廃棄物に最も適した所を最終目的地として選び、処分場とも正式に委託契約して適正化を実現した。 発生した産業廃棄物を処理業者に任せきりにせず、現場内でも発生した廃棄物が混合しないよう各自分別を徹底させ適正処理につとめた。 発生した産業廃棄物の数量が最終目的地で適正に処理されたことをマニフェスト により確認した。 不法投棄の防止のため、中間処理場、最終処分場までのルートについて現地確認した。 発生した産業廃棄物を分別し、混合しないよう間仕切等を設けた。 処理業者との委託契約は、実績のある信頼性の高い業者を選定した上で締結した。 事前に産棄の契約書で排出事業者、収集運搬業者、処分業者と三社契約を行い、 1台ずつマニフェスト伝票により管理を行った。 不法投棄が行われないように処分場所での管理を行い、必要によっては写真管理も実施した。 中間処理場までのルートを実際に確認した。 車両ナンバー一覧表と実際の運搬状況の写真 (ナンバー付 )を確認した。 中間業者及び運搬業者等の会社の資料と地図を事前に準備し、作業の間にマニフエストの提出及び指定業者への搬入を確認した。 運搬作業中に車に同乗し処分場への搬入を確認し、全体の数量も最後に確認した。 最終処分場に出向き現地確認するとともに、搬入量の検査を実施した。 発生した産業廃棄物が最終処分場で適正に処理されたことを、マニフェスト伝票で管理した。 産業廃棄物処理の許可がある業者へ処分依頼を行い、最終処分場の現地確認を実施した。 マニフェスト伝票管理によって、正しく処理されたことを確認した。 現場内ゴミを適切に分別し、正しい処理場で処分することとした。 産業廃棄物管理票により最終処分場までの工程管理を実施した。 産業廃棄物の最終処分地まで行き、きちんと処分されているか現地確認した。 マニフェストにより処分の状況を明確化する管理を行った。 |
地球温暖化

| 留意事項 | 地球温暖化 |
| 処置対策 | 使用していない重機はエンジンを止め、二酸化炭素の発生を抑制する。 ダンプカー、作業員の車、搬入車両のアイドリングを禁止とした。 工事車両や重機のアイドリングを止めることを徹底する。 昼休み・休憩時間は、現場事務所及び工事場所の通路以外の消灯を心がける。 重機及び工事関係車両の省エネ運転、アイドリングストップの励行、事務所等のスイッチの管理、不要な電気の消灯等による CO2の排出量の削減。 作業場内に乗入れを行うすべての車のアイドリングストップ運動を行い、 CO2削減に取り組み地球温暖化の防止意識の向上を行う。 現場搬入運搬車両のアイドリングを原則禁止とするとともに、公共交通機関による通勤を推奨し、マイカー通勤を減らすことにより、二酸化炭素の発生を抑制すべきである。 CO2を削減するために木くずを処理する処分業者を、木くずを破砕しウッドチップとして再販売する業者を選定した。 |
熱帯林の減少

| 留意事項 | 熱帯林の減少 |
| 処置対策 | マンションなどの同一タイプの多い住宅では、型枠をプラスチック型枠として材料を減らし、熱帯林を守る。 合板型枠からプラスチック型枠へ変更した。 型枠は鋼製型枠を利用して、合板を使わないようにする。 コンクリート型枠を木製からアルミまたは鋼製に変え、型枠そのものを使用するのを減らした。 木製型枠の転用及び鋼製型枠の使用促進に留意し、木材の使用低減に努めていく。 型枠工事の際に使用する型枠材料に木製型枠を使用せず、プラスチック製、紙製型枠の転用を行う。 型枠材を合板せき板から鉄製に変更し再利用を図り、熱帯雨林、森林保全の環境問題に対応した取組みを行う。 使用可能な部位の型枠材については、ラワン合板に替えてラス型枠、フラットデッキ、PC板等を使用する。 |
大気汚染

| 留意事項 | 大気汚染 |
| 処置対策 | コピーの裏面の使用。アイドリングの停止。環境対応建設機械の使用。現場内の緑化。 建設機械については、排気ガス対策ずみ (排ガス対応型 )の重機を使用する。 工事現場に入るすべての車両のアイドリングをストップさせた。このことにより大気中の CO2を少しでも減らした。 現場での重機・車両のアイドリングストップを関係者に教育し、その効果を現場にて確認した。 |
水質汚染

| 留意事項 | 水質汚染 |
| 処置対策 | 現場内処理水は、必ず所定のフィルター層 (砂利、砂層 )にて処理する。沈殿池の設置。 現場内で発生した汚水をそのまま下水に放流せずに、浄化ピットにて浄化し、下水に放流する。 |
資源の枯渇

| 留意事項 | 資源の枯渇 |
| 処置対策 | 解体の際に発生する鉄骨、鉄筋、コンクリートを分別し、専門のリサイクル業者にて再生資材として利用する。 リサイクル製品等のグリーン購入の積極的推進と熱帯材型枠に替わる代替型枠の 使用。 現場事務所でのコピー紙や不要図面の裏面使用により、紙の使用を削減し、木材資源の枯渇を防止すべきである。 長期材令管理のできる部位のコンクリートは、ポルトランドセメントに替えて高炉セメントを使用する。 建設発生土の利用を促進するため、近郊の現場所長と残土運搬業者との連携を図り、建設発生土の性質等の情報を提供し合うとともに、埋戻し現場に再利用を図った。 |
環境負荷の低減

| 留意事項 | 環境負荷の低減 |
| 処置対策 | 建設副産物の発生抑制現場から生じる建設副産物を最小限に抑えるため、各下請業者及び納入業者に対し、梱包材を減らした材料の搬入を要請した。また、各種仕上げ材料の選択に際しても、極力、梱包材を減らした材料や規格材の採用を監理者に助言した。その結果、これまでの現場に比べて、搬出される梱包材の量を約 20%削減することができた。 リサイクルの推進施設内の舗装工事に際し、既存施設の解体によって発生したコンクリートガラを再処理工場に持ち込み、再生用骨材として再利用した。また、車庫棟の基礎工事についても再生クラッシャーランを採用した。 |
高品質再生骨材を使用したコンクリート

| 留意事項 | 高品質再生骨材を使用したコンクリート |
| 処置対策 | 建設副産物の中で最も大きな割合を占めるコンクリート廃材は、建設副産物総排出量の約 4割を占め、そのリサイクル促進が環境保全、省資源のうえで大変重要となっている。これまでは建物の構造体以外の部分に使用が限定されていた。 |
| 結果評価 | 本工事では都内の解体工事の廃コンクリートを機械的に破砕し高品質再生粗骨材 (サイクライト )を再生する実機プラントにより粗骨材を回収し、構造のスラブコンクリートの一部に使用した。 本方式は、解体コンクリート塊をジョークラッシャーにより粒度処理調整を行い偏芯ローター式のすりもみ装置により 5~ 25mmの高品質再生粗骨材 (サイクライト )を製造するものであった。 |
環境配慮型施工

| 留意事項 | 環境配慮型施工 |
| 理由目的 | リデュース、リユース、リサイクルの 3つの活動は 3R活動と呼ばれる。本工事においては、 3R活動による環境配慮型施工が求められていた。 |
| 処置対策 | リデュース活動については、TOFT併用パイルド・ラフト基礎工法の採用による汚泥や残土の削減や、基礎躯体工事での合板型枠の削減、仕上げ材の梱包材やパレットの削減、さらには食堂の設置による作業員の弁当ゴミの削減などを行った。 リユース活動については、既存建物の解体ガラから再生した再生砕石や、外装材には廃ガラスカレット、ダクトや仮設事務所の机椅子には当社の紙ゴミからつくったダンボールを利用した。 リサイクルは作業所内に分別ヤードを設け、当社社員と作業員が一体となり掃きゴミ まで徹底的に分別した。 |
| 結果評価 | これらの活動の結果、混合廃棄物はゼロとなり、リサイクル率は 97.4%を達成できた。総搬出量は㈹建築業協会 (BCS)の目標値より 20%少ない 8.5m3/100m2、 CO2の搬出量は、建設業三団体目標値より 30%少ない 19.6kg・ CO2を達成することができた。 |
アスベスト含有建材の取扱い

| 留意事項 | アスベスト含有建材の取扱い |
| 理由目的 | 石綿のことで、綿のように軟らかな繊維だが、鉱物の一種で発ガン性があり白石綿を除き使用が禁止されている。 |
| 処置対策 | ●使用状況の調査・現在解体される建物には、アスベストが多少なりとも使用されていると考えたほうがよい 1.アスベスト建材を適切に取り扱うためには、解体する建物におけるアスベスト使用状況を調査する必要がある 2.解体・リニューアル工事においては、この調査および結果の記録が労働安全衛生法で義務づけられている 3.対象建物の図面が残っている場合でも、修繕などにより図面と異なる建材が使用されているケースもあるので、アスベスト含有か否かは、分析機関での分析結果に基づいて判定することが望ましい ●除去工事時の必要措置・除去時には、資格者の設置や事前届出を行う 1.作業場内は全面隔離する 2.養生・負圧除塵装置やクリーンルームを設置する 3.使い捨て作業衣や国家検定品マスクを着用する 4.廃棄時には、除去物だけでなく使用したシートや作業衣なども含めて特別管理産業廃棄物に該当するため、二重梱包またはコンクリート固化後管理型埋立処分するか、溶融による中間処理を行う。 5.スレートやPタイルなどの非飛散性アスベストについても、アスベスト粉塵飛散を抑制するため、機械解体を避けて手壊しし、中間処理施設での破砕を避けるために埋立て処分場へ直送することが望ましい。 ●リニューアル工事における留意点・アスベストを直接いじらないと思われても、天井面やダクト工事の吹付面へのアンカー取付け作業、設備機器類の撤去・取付け時などに、作業員や資機材がアスベストに接触する可能性も高いため、できる限りの除去を行う。 1.アスベストを脱落させ、結果的に劣化状況が悪化することも考えられ、建物使用者への人体影響や、将来の解体時の除去作業などを考慮し、リニューアルの対象となる区画については、できる限り除去する。 2.空調システムが天井チャンバー方式を採用している場合、耐火被覆にアスベスト建材を使用していると、アスベストに触れたリターンエアが再度室内に吹出されることになるため、アスベストを除去する必要がある。 |
| 建設副産物・環境問題への対策から施工経験記述を考える関連のページ |
|---|
| ・『環境管理』の施工経験記述を解く |
令和7年度版のオリジナル参考書が完成しました!
手元に参考書が欲しいという方は下記サイトで販売をしています。
A4用紙で243枚分というかなり濃い内容となっています。
※参考書には、このサイトに掲載がされていない情報も沢山載っています。
どこでご購入をされても内容は同じです。
『一級建築施工管理技士』で検索をして下記の画像を探してください!
お急ぎの方はデータでの販売も行っています。
※すでにPayPalアカウントをお持ちか、新たにアカウントを開設された方に限ります。
Paypalの新規登録(無料)はこちら⇒ Paypal公式サイト
掲載内容
1.過去19年の出題傾向
年度ごとに詳細をまとめました。これをじっくりと分析することで、これまでの流れが見えてくるはずです。さらに、その流れを読み解けば、次年度にどのようなテーマが出題されやすいのかを予測する手がかりになるかもしれません。
2.今回の見直しで第二次検定の経験記述はどう変わったか?
今回の具体的な変更点や、これにどう対応していけば良いのかについて、この参考書で詳しく解説をしています。また、参考書の効果的な活用方法についても分かりやすく説明をしています。
3.平成18年度~令和6年度の本試験解答例
試験対策として過去問を理解することは基本です。そして、昨年度に第二次検定の見直しが実施されましたがそれでも過去問を捨てることは出来ません。繰り返し見ていると、どういうところが設問として出やすいのか見えてくると思います。
4.構造種別 経験記述例
新築工事において特に重要な、主要構造の3種類(鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造)に関する施工例を豊富に取り揃えています。さらに「おまけ」として、新築工事だけでなく改修工事に関する施工例も追加しました。
5.業種別 重点対策問題
受検者には、専門工事業の方が多い現実を踏まえ、この参考書では全17業種にわたる解答例を準備しました。そして、実際の施工現場を想定した具体的で実践的な内容により、各業種ごとの特徴を踏まえた解答を分かりやすく解説しています。
6.一問一答式
試験対策に役立つ解答の「引き出し」として、知識を効率よく整理できる一問一答形式の内容を加えました。そして、この形式では、試験で問われやすい内容を厳選し、要点を簡潔にまとめています。忙しい受検者の方でも、スキマ時間を活用して効率的に学べる工夫を盛り込んでいます。
7.建設副産物・環境問題への対策
建設副産物の適正な処理や環境問題への対応は、建設業界における重要な責任であり、未来に向けた永遠の課題と言えます。そして、SDGs(持続可能な開発目標)を意識した建設活動や、最新の法規制を考慮した実例も収録。これにより、試験対策だけでなく、実務での活用にもつながる内容となっています。
8.経験記述の良い書き方・良くない書き方
同じ内容でも、記述の仕方一つで採点者に与える印象が大きく変わります。さらにこの章では、採点者の視点を意識した「良い記述例」と「良くない記述例」を比較しながら、効果的な表現方法を学ぶことができます。
9.施工経験記述はこの3つ!
施工経験記述の出題傾向を分析した結果、対策すべき課題は3つに絞ることができます。そして、これら3つのテーマごとに、出題ごとの解答の注意点や重要な記述のポイントをまとめています。この章を読み込むことで、施工経験記述の対策は万全です。
10.令和7年度予想問題 鉄骨(S)造・鉄筋コンクリート(RC)造
令和6年度は「鉄筋コンクリート(RC)造の合理化」でした。これまでの流れで考えると、令和7年度は「〇〇造の〇〇〇」。この章では鉄筋コンクリート(RC)造、鉄骨(S)造での品質管理・合理化・環境管理それぞれ6パターンでの設問と解答例を考えてみました。ヤマを張ることはオススメ致しません、しかし対策は必要です。
過去問データからの施工経験記述対策
- 過去19年の出題傾向
- 見直しで施工経験記述はどう変わった?
- 施工経験記述 過去18年分の本試験解答例
- 構造種別 施工経験記述例
- 業種別 重点対策問題
- 施工経験記述 解答参考例
- 応用問題が出ても怖くない!一問一答式で対策
- 建設副産物・環境問題への対策から経験記述を考える
- 施工経験記述の良い書き方・良くない書き方
- 独学でも出来る!施工経験記述はこの3つ!
最新の施工経験記述対策メニュー
1.鉄骨造パターン
2.鉄筋コンクリート造パターン
二次試験へ向けて有効活用致しましょう♪